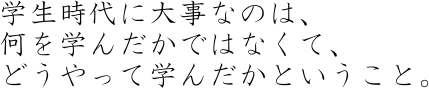未来のテレビは? 久夛良木氏「Eee PC化する」 麻倉氏「壁になる」 という久夛良木氏の話を含む記事が09年3月に公開されていた。
spiderという一週間の全番組を録画するサーバが視聴環境を変えたという話から、検索やレコメンドがあればネットとテレビの関係が変わる的な話があり、興味深い。
この記事から、久しぶりに自身のテレビ観について顧みることにした。
テレビの未来について、「放送と通信の融合」がもてはやされた時代にそれなりに真剣に考えた時代があって、その頃の考えでは”ほとんどの家庭がホームサーバを持つようになる”、”ホームサーバが家電を操作するが、そのコンソールパネル的な役割をテレビが担う”、”テレビでネットのコンテンツにアクセスできるようになる”ということを考えていた。この前提から”ホームサーバの需要が高まる”とし、ホームサーバの前提があればアドホックネットワークの導入のコストも低くなるので活用の場(例えばご近所的なネットワークでも)も広がる、と考えていた。
そこで無線が重要だということでそのような取り組みを行ってきた。その取り組みでは高精細テレビと無線の双方共に関係する取り組みが出来て面白かった。
それから時間を経ることによって、”ホームサーバの必要性”、それに基づく”アドホックネットワーク活用”、”テレビにおけるネットコンテンツの視聴”などの自身の過去の主張について、懐疑的な視点を持つようになった。それを本当に人は喜ぶのか、という点について疑問が沸いている。
考えていた当時としては、インターネットコンテンツのシームレスなアクセス環境を身近で分かりやすい所に用意することで、勝手に人はアクセスして楽しむはずだという考えがあった。しかし、この人は勝手にアクセスして楽しむはずだという点については、本当にキラーなコンテンツ(本能的なコンテンツ)が存在しない限り、壁を越えたりしない。
例えば具体的な例でいえば、PS3やWiiはホームサーバと見ることができるが、ネットワーク端末として活用されていないことに若干の失意を覚えている。これらのゲーム機は常時ネットワーク接続を行うことができ、かつ演算機能を備えているので、狭義のホームサーバと捉える事ができる。物によっては無線ネットワークにも対応する。しかしながら、常時利用の情報端末として扱われていないと、勝手に自分の中で想像している(実は違うのかもしれない)。
これらの端末の持つポテンシャルは高く、Wiiでさえyoutubeを再生することのできるパワーを持っている。2007年にITmedia News:YouTubeをテレビで“ダラ見” はてな、Wii対応の動画サービスというサービスが公開されたが、このようなネットでありながらも受動的なサービスがより提供されてくるだろうと期待をしていた。
が、そのようなことはなかった。Webの世界の人間には受け入れられなかったのだろう。個人的には”テレビの能動的メディアへの歩み寄り”を中心に考えてきたが、最近では”ネットの受動的メディアへの歩み寄り”も面白いと考えるようになってきている。
それはディスプレイのサイズが作業スペース以上に広くなってきている点やディスプレイ余り現象なども含めて、そう思っている。Windows Vistaでは右にサイドバーが出現するようになった。このサイドバーに乗るアプリのことをガジェットと呼ぶ。このサイドバーを嫌う人が多いかもしれない(自分は嫌いだ)が、このガジェットは狭いディスプレイをさらに狭くするためのものではない。24インチディスプレイのように使い切れないディスプレイを有効活用するようなものだ。また液晶ディスプレイ価格は低下しており、あまっているケースもあるかもしれない。この枠に受動的メディアが入る可能性もあるのではないかと考えている。
この受動的メディアの中身については、中心は映像だが、映像以外のコンテンツが存在するのかどうか思考してみると、むしろ存分に有り得るのではないかとも想像している。インターネット上には映像以外の面白いものが文章だったりイラストだったり、写真だったり、漫画だったりと多岐に渡って存在する。それをどのように”ながら見”に対応させるのかが映像以外のコンテンツの課題となる。
”ながら見”の課題解決法の1つとして、最近はフォトフレームに着目している。フォトフレームとは例えば日本サムスンからUSBサブモニタになる8インチ デジタルフォトフレームのようなものだ。現在は8インチ台の液晶を載せたフォトフレームが多く出回っているように感じる。
フォトフレームでは、退屈な写真の表示を改善するためにスライドショーを行う。ただ単にスライドショーを行うだけでなく、BGMをつけたり画面効果を狙ったりなどを行えるような製品も出ている。このフォトフレームの利用法の発展として、例えばネット上の面白写真やイラストを表示させたり、仕事に関係のある最新のニューストピックや経済状況・株価などを表示させることで、1つの受動メディアとして面白くなるのではないかと感じている。具体的にはYahoo!プロ野球などでは野球の試合中にコメントの投稿を受けつける画面が存在するが、そのようなコメントを8インチディスプレイで閲覧しながら、野球を観戦したら面白いのではなかろうか。この例は野球などのスポーツに限らない。
受動的なメディアについて書いてきたが、能動的に探して閲覧するメディアは、現状でそれなりに数が揃いつつあるが、その操作性に問題があると感じている。例えば親父殿がパリーグの試合をYahooプロ野球で見たいという状況に遭遇した場合、PC上での操作で見られるように準備を行うという行為はなかなかに面倒くさい。テレビのチャンネルの1つに登録できたらすっごい楽で、日本中の人が見るのにな、と思うことがある。
逆に見れば操作性のハードルは誰にでも分かるもので、誰かが実現してくれるだろうことは明らかなので、誰かがYahoo動画(のパリーグ試合)を簡単に見られる機器を開発してくれるのを待つばかりだ。
#
と、日ごろ考えているうっぷんを書いて、すっきりしてみた。
ディスプレイは本当に安い。パソコン・PCパーツ通販ショップ – ドスパラ見ると、24型フルHDが24,000円だったり、21.5型フルHDが17,822円だったりで、つい買ってしまいそう。PS3持っているのに普通のテレビに繋いでいるという人の話が入ってきたので、安くてもいいから買ったら?と提案してみている。